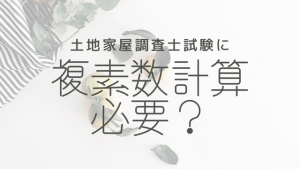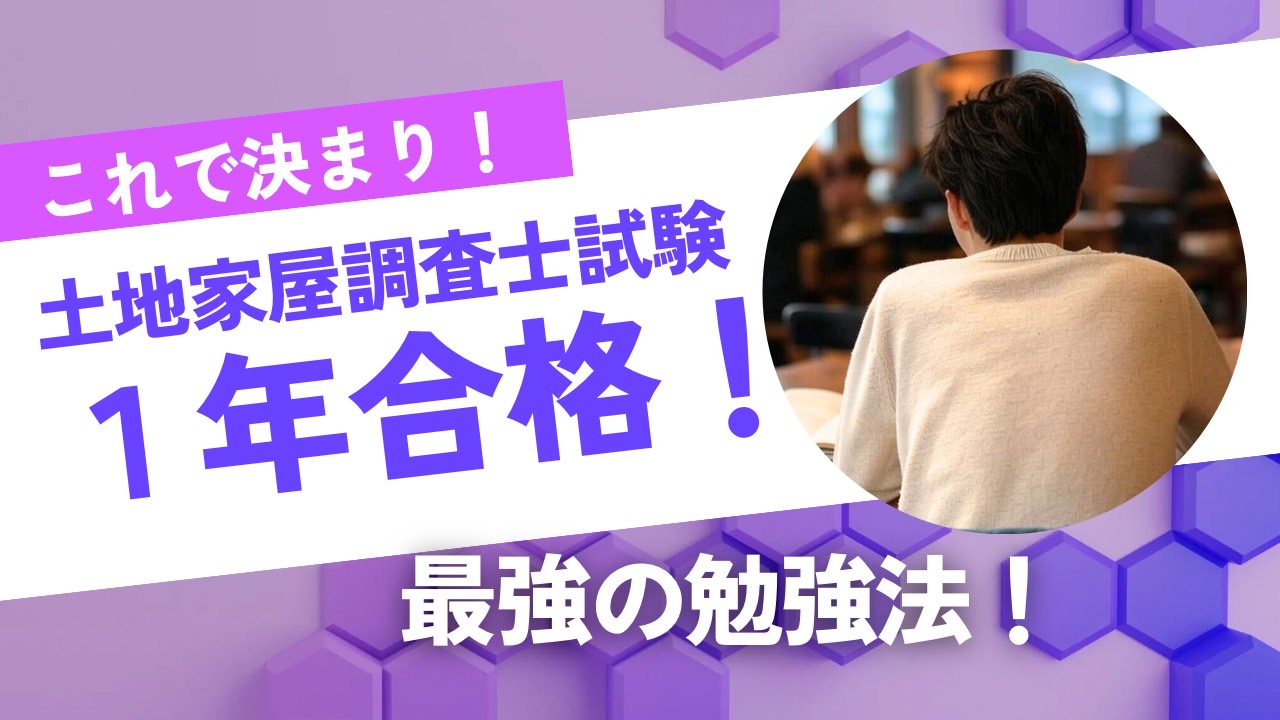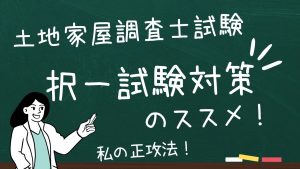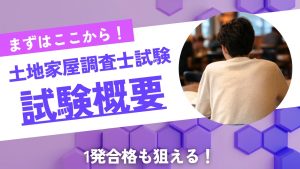こんにちは、土地家屋調査士合格を目指す皆さん!試験勉強の進捗はいかがでしょうか?
今回は、土地家屋調査士試験の短期間合格(1年合格)までの具体的な勉強計画を、ご紹介します。
これで1年で合格への道がぐっと近づくはずです!
テキスト一周&択一問題集3周:基礎固めの鉄則!
まずは、基本のテキストを一周読みましょう。
土地家屋調査士試験は「狭く、深い」知識が求められる試験です。
予備校を利用されている方は、対面講義や講義動画を通して、調査士試験の大枠をつかむようにしてください。
テキストを1周が完了したら、択一の問題集に入っていきましょう。
不動産登記法を中心に、民法や土地家屋調査士法などの関連法規をしっかりと理解することが重要です。その後、択一問題集を3周解きます。
この時点では、わからない問題は深追いせずに次に進んでいきましょう。
問題を繰り返し解くことで、知識の定着と問題形式に慣れることができます。
択一の問題集3周を完了したころには、ある程度択一が解けるようになっているかと思います。
GW連休前にはここまでは最低限終わらせておきましょう。
また進捗が早い方は、4周目に入りましょう。
問題集4周目からは、わからないところはテキストや予備校の質問制度を利用して、間違いを減らす努力をしていきましょう
GW前後に複素数と図面の書き方を攻略!
ゴールデンウイーク前後の期間を利用して、複素数や図面の作成方法を集中的に学習しましょう。
測量に必要な数学の知識は、角度計算や三角関数(サイン・コサイン・タンジェント)が中心です。
これらの計算は電卓を使用して行うことができるため、公式の理解と計算手順を身につけることが重要です。
また、図面作成に関しては、三角定規を使った基本的な作図技術を習得することで、試験で求められるレベルに十分対応できます。
ゴールデンウイークが終了後にはいよいよ記述式問題に入っていきますので、この1、2周間はわき目も降らずに測量計算(複素数)と図面作成の技術を完成させましょう!
GW明けから試験2か月前まで:記述式と択一をまとめていく!
GWが明けたら、記述式問題と択一問題の総合的な練習に取り組みましょう。
ここでは、択一式と記述式の問題を時間を測りながら進めていきましょう。
特に、択一式は30分以内で解くことを目標にしましょう。
記述式問題では、実際の登記申請書や添付図面を作成する力が求められます。
ですが、記述式問題は複数回解くことで解法を覚えてしまい、本試験のような新鮮味が無くなってしまうので、1問1問丁寧に解いて行くように注意してください。
8月上旬ごろまでは過去問活用して、実践的な練習を積み重ねることが重要です。
この期間に本試験で戦える土台作りを徹底しましょう。
また、択一問題についても、繰り返し問題を解くことで、知識の確認と弱点の補強を行い、適宜テキストを読み返すことで過去問の間違いは必ず無くしていきましょう。
直前期:答練はほどほどに!
答案練習(答練)は有益ですが、過度に熱中する必要はありません。
自分のペースで学習を進め、必要に応じて活用する程度で十分です。答練は、自分の理解度を確認し、弱点を把握するためのツールと位置づけましょう。
私の場合ですが、あくまでもテキストと過去問を基本として、実力テスト的な意味合いで週1日だけアガルートの答練(全6回のみ)を実施していました。
答練は難易度が高いものが多いため、本試験で出ればみんなが解けない問題であるケースが多いです。
過去問とテキストを完璧にすれば十分合格できますので、答練はコーヒーブレイク的な使い方が望ましいです。
まとめ
今回は試験までの勉強法を紹介しました。
これからチャレンジする方は是非参考にしてみてください。
私の場合は、上記スケジュールで1月から勉強開始しましたが、無事に1発合格できました。
私が思うには調査士試験は過去問試験です。
とにかく過去問とテキストを周した人が受かる試験ですので、いろいろな問題に手を出さず、過去問を完璧に仕上げてください。
皆さんの合格を心から応援しています!一緒に頑張りましょう!