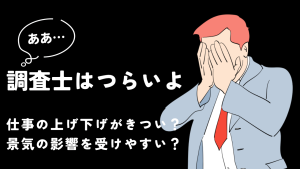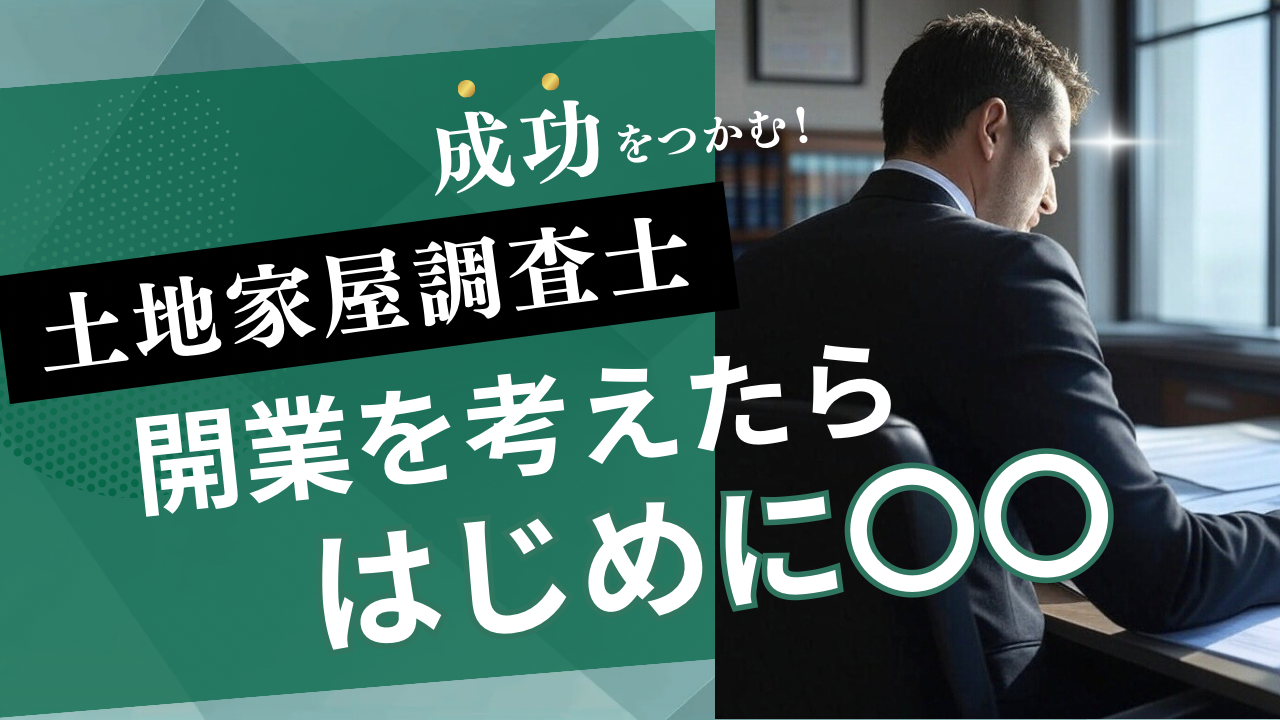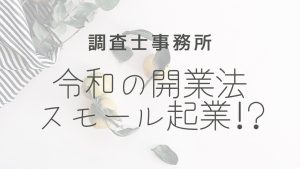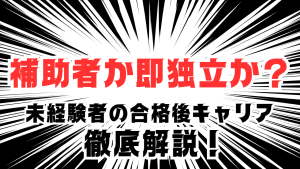皆さんこんにちは! 土地家屋調査士のMr.Takaです。
「土地家屋調査士試験に合格したけど、これからどうする?」
今回は独立開業を考えはじめたら、まず知ってほしいことを紹介します!
私は開業でいろいろと後戻りがあったのでぜひ開業の準備に役立ててください!
独立開業準備の第一ステップ!
それは何だと思いますか?
それは綿密な資金計画と、新規顧客獲得です!
現在はサラリーマンや他の業種で独立して働いている事かと思います。
土地家屋調査士として開業するには測量機器、CADソフト、PC、プリンターなど多岐にわたります。
また、何と言っても「事務所」です。持ち家であれば一部屋を事務所として使用できますが、賃貸であれば事務所に使用できないことも多く、別に事務所を借りる必要がある方も多いかと思います。
当然に開業資金が大きな額となりやすいことから新規顧客の獲得は開業後の課題になります。
開業を考えだしたら、今の仕事を辞める前に、綿密な資金計画と新規顧客獲得について考えてみてください。
資金計画の立て方
それでは資金計画について考えていきましょう!
まず、開業にかかる費用は事務所設備や測量機器など初期投資として必要な額を把握することが重要です。
具体的には、以下のような項目が挙げられます。
・事務所設備:賃貸事務所、電話・FAX、コピー機や複合機、CADシステム、申請用システム、専門書籍など
・測量機器:トータルステーション、測量用プリズム、三脚、コンベックス、巻尺、レーザー距離計など
・現場用車両:軽自動車など小回りの利くものが望ましい
(ミラ、アルトのように狭い軽自動車でも何とかなります。)
これらを合計すると、開業費用は約200万円~1,000万円程度となってしまいます。
開業資金の削減
上記金額はすべてを揃えた場合であり、一つ一つ取捨選択をすることで費用を抑えることができます。
例えば、自動車は既にマイカーがある時はそれを軌道に乗るまで現場用としても使うことができますし、賃貸事務所は借りずに自宅開業とすることもできます。
その他にも事務所の固定電話は置かず、すべて携帯電話にすることも考えられます。
このように、固定費を削減していくことで開業資金をグッと抑えることが可能になります。
また、経営上のリスクを大きく下げることができます。
土地家屋調査士は、BtoB業務が大多数を占めるため、自宅開業や携帯電話のみでもあまり機会損失はないと考えています。
私は本年度からFAXを解約しましたが特に問題は起こっていません。
開業融資制度の利用
政策金融公庫などの創業融資を利用することもオススメです。
創業融資は創業時にしか借りることができない、優遇金利で審査も通りやすいし比較的据え置き期間(元本返済を先延ばしにできる制度)も長くとれるオススメの融資メニューです。
一旦開業期を過ぎると売上げが上がりだすまでの数年間は確定申告の額も少なく(又は一時的に赤字のため)通常の融資は降りないことも多いため必ず利用の有無だけは検討すべきです。
私は開業資金をかなり抑えたのですが、トータルステーションだけは1人で作業できるメリットを考えて自動追尾にしました。
自動追尾はかなり高かった(新車ファミリーカー1台くらい)ので、創業融資をトータルステーションとCAD(安い軽自動車くらい)に充当しました。
しかしながら今考えてみると、機器購入の設備投資として借りただけで、運転資金を借りなかったため、はじめのうちは仕事が無く毎月減っていく預金額にひやひやしましたし、非常に苦労しました。
我ながら危険なことをしたなと改めて思います。
調査士業務は資金回収サイクルが半年~数年となることも珍しくないことから、潤沢な運転資金を用意することが経営のカギと言えます。
また、選択する機器や設備によって費用は変動するため、自身の予算やニーズに合わせて計画を立てることが大切です。
顧客獲得のための戦略
開業後、安定した業務を確保するためには、効果的な顧客獲得が不可欠です。以下の方法を検討してみましょう。
退職前にできること
まずは今の仕事をしながら、不動産業界、建設会社の多く集まる場に顔を出すことです。
交流会などは比較的大きな都市では開催されていることも多いため活用するといいかもしれません。
その他、例えば仕事のつながりや知人などを当たってみて、自分がいつ開業するかを伝えてみるのもいいと思います。
開業することを多くの人が知ってくれる(露出を増やす)ことが、仕事をスムーズにとる営業活用の一つになります。
退職後(調査士登録後)にできること
無事に退職し、調査士登録後(開業後)は、とにかくやれることは何でもやっていくことになります。
厳しい言い方ですが、弱肉強食、ベテランやあなたよりも賢い敵と戦うことになります。
しかしながら、平均年齢の比較的高い土地家屋調査士事務所は営業せずとも仕事を抱えているケースも多いので、下記の営業ツールを試してみるのはいかがでしょうか?
グーグルマップなどに掲載(MEO対策)
ホームページを作成(SEO対策)
SNS戦略(主に企業向け)
飛び込み営業
ここで列挙したものは上から順に優先度が高いと思います。
マップに事務所位置を掲載することや自社ホームページを持つことは、利用するか迷っている顧客層へ有効にターゲティングすることができます。
飲食店やホテルなどと同じく、調べてみてちゃんとしたホームページがある事務所、グーグルマップに掲載されている事務所に依頼したいものですよね。
※ホームページは作成後、SEO対策をしたとしてもヒットしやすくなるまでに時間がかかるため、ここではマップサービスの方が優先度が高いとしております。
その他、SNS戦略を打つことも効果的です。具体的には、インスタグラムやX(旧Twitter)で調査士事務所の日常や担当者の顔を紹介することなどが効果的です。
また、SNS戦略として重要なのは、アピールする顧客層は個人ではなく、他士業事務所や不動産業界、建設業界となることです。
不動産担当者や建設会社などは受注にSNS戦略が調査士以上に必須となってきているの業界ですので、その担当者と繋がることができるのがSNSを利用する最大のストロングポイントです。
そしてそれでも効果が出ない時は飛び込み営業をすることになるでしょう。
しかしながら、飛び込み営業は既存の土地家屋調査士がいる場合は特に反応が悪く、金額面でもディスカウントを要求されることが多いため経験的にあまりお勧めできません。
それでも、今も付き合いのある良い業者様と知り合えたことも事実ではあります。
しかしながら、ネット全盛期の令和の時代には効率は悪いと思います。
絶対にNGなこと
開業準備で絶対にNGなことは、他の調査士事務所や士業事務所、不動産・建設会社と険悪な関係になることです。
これは、言うまでもなく、県単位で同じエリアの他業者は横のつながりも密ですので、悪いイメージが先行してしまうと、せっかくの営業活動が台無しになっています。
現在は補助者として働いていて、これから独立するとしても、その調査士事務所は従業員と雇用主の関係から、本職同士の関係となっていきます。
元居た事務所を慕えば、開業後の広告塔になってくれることも考えられます。
調査士業界は狭い世界ですので、ぜひここはグッとこらえて、礼儀を尽くして円満に退職されることを強くお勧めします。
まとめ
土地家屋調査士としての開業は、多くの準備と計画が必要ですが、特に重要なのが、しっかりとした資金計画と効果的な顧客獲得戦略を立てることです。
この二つがしっかりできれば必ず成功への道が開けます。
アピールの際は自身の専門性を活かし、取り引き先に貢献できる部分を熱意をもって伝えていけば多くは無くても少なからず営業は取れます!
また、人間関係もできるだけ大切にするよう明日から心掛けましょう!
以上、土地家屋調査士として開業を考えている場合は参考にしてみてください!